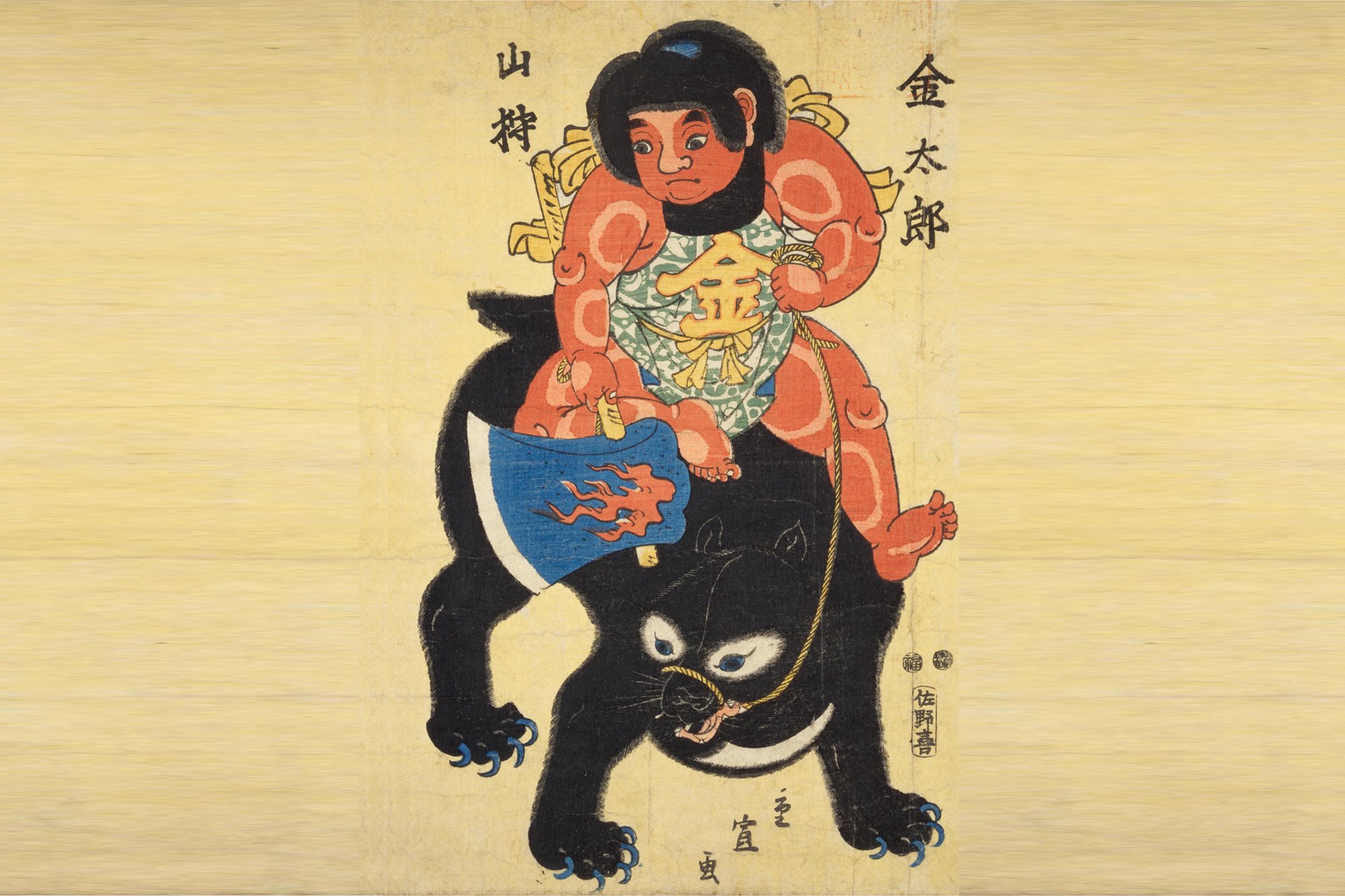relay essay|連閏記
16|クマとコロナとスズメバチ
宮下 直(生態学)
今年の秋は全国各地でクマが出没し、テレビや新聞をにぎわせた。日本には本州と四国にツキノワグマ、北海道にはヒグマが生息している。ツキノワグマは普通の人の体重と同程度だが、ヒグマは150〜200㎏ほどあり、大きな相撲取りほどもある。クマはイヌやネコと同じ食肉目に属するが、動物質も植物質も食べる雑食性である。ツキノワグマもヒグマも餌の多くは植物の葉や根だが、ハチなどの昆虫や魚も捉えて食べる。ひとことで言えばクマは山で暮らす動物で、人里に下りてくることはめったにない。だが、今年は山の堅果類(クリやドングリ、ブナの実など)が不作だったらしく、驚くほど多くの個体が人里や市街地にまで出てきた。以前は庭や畑のカキの実などの好物を狙ってのことだったが、今年は牛の飼料や作物の肥料など、クマがとても食べるとは思えないような物にまで手を出している。よほど餌に困窮してのことだろう。山の木の実が不作だったのは長く続いた猛暑が原因とされているが、科学的に実証されてはいない。だが、今年は山野で昆虫を見かける機会がめっきり少なかったことを考えると、極端気象が原因というのは頷ける。
日本のクマは人と比べて何倍も大きいわけではないが、鋭い爪と桁外れのパワーを秘めている。もう20年近く前になるが、名の知れたプロレスラーとツキノワグマが格闘するテレビ番組があった。口輪をあてがわれ、爪も切られた哀れなクマだった。両者の体重はほぼ互角だったが、体がぶつかった瞬間、プロレスラーの肩が脱臼し、戦闘不能になった。クマのパワーだけで、鍛えられた人間がいとも簡単に倒されてしまったのだ。今年出没しているツキノワグマは、多くが子連れの雌である。雌の体重は成人と同程度だが、本気で襲われれば命にかかわる。子グマでも素手では大怪我をしかねない。ヒグマが相手であれば、まるでぼろ雑巾である。
生き物の脅威はクマだけではない。都市緑地や郊外の林に棲んでいるスズメバチは、毎年夏から秋にかけて多くの刺傷事故を起こしている。ハチは群れで襲撃してくる恐ろしい生物だが、体内に注入された毒物質に対して私たち自身が起こすアレルギー反応が深刻である。アナフィラキシーとして有名で、過去に刺された経験のある人は死に至ることもある。そんな危険なスズメバチの巣は、ほぼ間違いなく駆除される。そもそもクマのように保護や保全の思想がないので、駆除に反対する人もいない。だが、スズメバチは巨大なコロニーを作るため、自然界で大量の餌を消費している。餌のほとんどが植物の葉などを食べる昆虫である。もしスズメバチが根絶すれば、これら昆虫が大発生し、植物を食い荒らして大きな被害を与えるかもしれない。農耕地であれば、作物被害になるだろう。スズメバチは鳥類と並んで、害虫の天敵として、自然のバランスを保つうえで重要な役割を果たしている。
自然界における生き物の脅威をもう一つ挙げるとすれば、感染症を引き起こす病原体だろう。新型コロナウイルスによるパンデミックから明らかなように、古今東西を問わず、感染症ほど万民にとって恐ろしい「生き物」はいない。そのインパクトはクマやスズメバチとは比較にならない。感染症にはウイルス以外にもバクテリアや原虫なども含まれる。肉眼では見えないが立派な生き物たちである(学術的にウイルスは生物とはみなされないが、ここでは広義に扱う)。感染症の制圧は撲滅と言い換えることができる。これにはスズメバチ以上に異論を唱える人はいないはずだ。だが、ここにも重要な副作用が潜在している。コロナ禍では、手をアルコールで徹底して消毒することが推奨された。強い感染力からすれば、理にかなった処置である。だが、その習慣はいまだに残っている。アルコール消毒はコロナウイルスだけでなく、多種多様な微生物も殺す、いわば微生物殲滅作戦である。逆説的であるが、その習慣が人間の健康に大きなリスクをもたらす可能性がある。過去30年間の研究により、花粉症や喘息などのアレルギー疾患は、体表や腸内に棲む微生物が減ったことが原因であることが明らかになっている。微生物は、かつて「ばい菌」とほぼ同義に扱われたが、大多数の微生物は人間に害をなすことはなく、むしろ体内の免疫バランスを維持するうえで役だっている。
物事は完全な善悪に分別されることはなく、光と影、表と裏、メリットとデメリットという矛盾を併せもっている。生物は私たちに様々な恩恵をもたらすが、時として牙をむく。それこそ自然の本質である。こうした多面性をもつ自然とどう折り合いをつけていくか、私たちは科学的根拠に基づいた広い視野から向き合っていく必要がある。